Special Talk:識者に聞くコーポレートガバナンス 宮内義彦×芳賀裕子
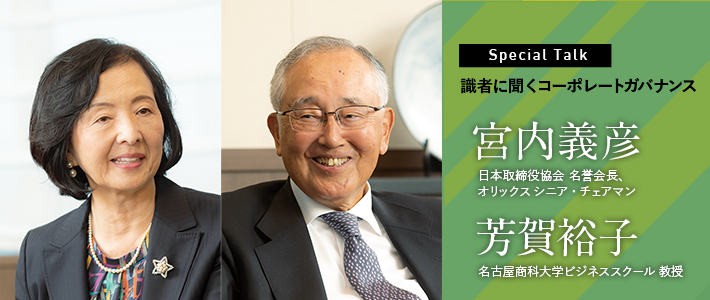
2025年5月15日
宮内義彦(日本取締役協会 名誉会長、オリックス シニア・チェアマン)
芳賀裕子(名古屋商科大学ビジネススクール 教授)
日本経済の成長とコーポレートガバナンスの必要性
企業統治(コーポレートガバナンス)を識者に聞くインタビューシリーズ。今回は宮内義彦・日本取締役協会 名誉会長をゲストにお招きし、日本経済の課題やガバナンス改革のあり方などを伺いました。この中で宮内氏は日本経済の生産性を高めるには、企業にガバナンスの徹底した経営を促す一方、政治が分配を適切に実施する必要性を強調しています。聞き手は名古屋商科大学ビジネススクールの芳賀裕子教授です。
芳賀 本日は日本取締役協会 宮内名誉会長に、日本経済の成長とコーポレートガバナンスの必要性についてお話を伺いたいと思います。
最初に現状、例えば、株価の高騰や、円安による日本経済の回復という見方がある一方でGDPの伸びの低下、上場企業のPBR低下、少子高齢化の問題など、国力の弱さが表面化しています。このあたりの現状と課題について、どのようにご覧になっているのでしょうか。
宮内 日本の経済システムは民主資本主義という形をとっていると思います。これは最も好ましい構造だと思いますが、中身を分解すると2つに分けることができます。1つは経済的な価値の創造という意味での「生産部門」、2つ目は生産したものをどう分けるかという「分配」の部門、この両方がうまくいかないといけない。生産部門については、まさに資本主義の原則である市場経済をできるだけ貫き、企業間競争をつくり出すことによって、生産効率を上げるのです。日本経済がGDPも伸びない、生産部門が上がらないのは、資本主義の中の鍵である市場経済がうまく機能していないところがあるのです。
また分配については、我々のような企業社会に関わっている人間が決定権を持つべきではありません。自然にまかせると市場経済で勝った者が1人勝ち、負けた者は残念でしたということになり、野蛮な分配の仕方になってしまうので、そこに介入するのがまさしく政府だと思います。分配については政府の力がものすごく大きい。政府は何をすればよいかというと、その社会が安定するような税制、補助金等の仕組みをつくり分配をすることだと思います。
市場経済と政府の分配のどちらもうまくいくと、素晴らしい世の中となるわけです。それを日本に当てはめた場合、まず生産についていうと、GDPが伸びない原因は2つあり、1つは参加する人間が減っているので小さくなる。中身をみると働く人が老齢化し、放っておくと縮小していくわけです。これに対する手当ができていない。女性の参加や働く人の年齢を上げていく、海外からきてもらう、いずれもやっていますが、不十分です。
もう1つの伸ばす手段としては、生産性向上という武器があります。生産性向上が労働人口の縮小より上回れば経済は伸びますが、なぜ日本の生産性が向上しないかというと、生産性向上を阻害する要因がたくさんあるからです。まず市場原理が貫徹するようなシステムになっていない。例えば規制改革、ほとんどが岩盤のような規制で止まっている。これを変えたらよいとわかっていても、既得権益が岩盤のようにたくさんできている。それから政策的にも、市場原理を阻害するような政策が多く、1例ですが1社たりともつぶさないというような中小企業対策。必要とされない企業が淘汰されなければ、効率が下がるのは当たり前ですが、そういうことを一生懸命やっている。市場経済の中で競争しているのは誰かというと、企業です。しかし、その企業も十分競争しているかというと、楽な方に傾いているし、コーポレートガバナンスも十分きいていない。言葉ばかりで、実態は企業活動を効率化するような動きにはとてもなっていないという問題がある。
分配については、表面的には日本は格差が少なくなるような、税制や経済政策をやっていて、そういうことでは世界の中で比較的よくできている。しかしそれは政府が立派なのではなくて、よく見ると財政支出、いわゆる借金だらけになりながら格差を小さくしている。ひょっとしたら課題を先送りしているだけかもしれないのですが、一応表面上は、格差が拡大してデモが起こることにはなっていない。しかし実際には底辺に沈む人が増えています。これは大きな問題です。ほかの国に比べたらずっとよいですが、日本だけを時系列で見ると、日本が総中流といわれていたのがいつのまにか中流から落ちてきているという問題を抱えているというのが、私のみる日本経済です。
芳賀 ありがとうございます。生産と分配の両方がうまく機能してよい資本主義社会になる。わかりやすい全体像の捉え方だと思います。全体像をお示し頂いた日本の中で、生産性のお話が出ました。生産性の低さ、今いくつかご指摘がありましたが、ここに焦点を当て、その低さの原因というのは具体的にいうとどんなところでしょうか。
宮内 大きく捉えれば、生産性を上げるにはインフレになればやりやすい。ところが、デフレ基調のままで、その対策もうまくいっているのかどうかわかりません。物価が上がっていき、高いものを買ってくれることが、表面的に生産性が上がる基本だと思うのです。一番基本のところがうまくいっていない。なぜかというと、ここ10年は金融緩和をやっただけです。金利をゼロにして、資金を充分に出すとみんなお金を使ってくれるだろうと思ったら、みんなそれを蓄えて安いものを漁るようになるという、逆の方向へいってしまった。金融緩和はやろうと思ったら簡単にできるわけですが、本当にやらなければならないのは経済の構造改革です。その中の、大きな部分が規制改革、既得権益をなくしていくことです。それにはほとんど手がついていないといっていいぐらいです。そのツケが溜まってきているのだろうと思います。

生産性を上げようと思ったら、大胆な構造改革と金融緩和が一体になって、やっとポリシーとして十分なのだろうと思います。片方でやったら何の意味もなかったわけです。それから、つまらない経済政策をしない。生産性の低いところへ補助金を出し、生きながらえるようなことをやっていますが、もっと生産の部分については厳しく、強者がしっかり勝って弱者は退場するという市場経済を作らなければならない。弱者が退場するのはかわいそうだという意見が多いですが、倒産は経営の失敗であって、マーケットがいらないといっているのだから消えないといけないのです。それによって失業する人がかわいそうなのであって、倒産を防ぐのではなく失業に対する対応をしっかりするべきです。そして彼らをもっと生産性の高いところへシフトしていく。そういう政策をとらないといけない。どこかビジネスより政治を優先しているような気がします。
芳賀 2020年代に入ってからも解雇規制の見直しについて、いろいろと議論されましたが、何も変化していません。一方労働市場そのものは変化しています。労働者の視点に立った解雇規制の緩和はできないのでしょうか。
宮内 金銭解雇をしたら叱られるとか、移民といった途端に選挙に落ちるなど、経済原則からみると、日本社会は妙なところです。例えば中小企業をつぶしてはいけないというのは、資本主義だったら退出しろといったら、資本金だけの損失で終るはずです。中小企業は資金を出資より借入に依存しているため、自宅も担保に入っているし、個人保証もしている、身ぐるみ剝がれるというように、今の日本では本当の意味での資本主義になっていません。
芳賀 一旦退出したとしても、本来はその経営者が別の形で再チャレンジできる環境がなくてはいけませんね。今マクロ側のお話をいろいろ伺いましたが、ミクロ側の企業のコーポレートガバナンスも含めたところの課題としてはどのようなものが挙げられるでしょうか。
宮内 ミクロで考えると、経済を活性化させているのは市場です。企業は市場の競争に勝たないといけない。競争に勝つというのは、買い手からみて優れたモノ、サービスをつくり出すことです。市場経済は完全に買い手が選別します。ところが、買い手からみて買うものが1つしかなかったら市場経済にならない。そういう意味では、例えば電力のように、独占色が強くならざるを得ないインフラ的な事業に対しては、もっと厳しく競争原理を入れ込む政策をやらないといけないのに、今もほとんど元のままという実質の乏しいことをやっています。
私も規制改革にずいぶん関わりましたが、一生懸命努力しても実態は変化なく、こんなことのために努力したのかというようなケースが多かった。例えば、日本みたいに高温多湿で肥沃な土地を持っている国は少なく、本当は大農業国になってもいい。しかし、農業に市場原理を持ち込むのはタブーで、米を作らなければ補助金が出る、消費者は品不足で高価なものを買わざるを得ないとか、考えられないような政策をやっている。それが政府の仕事だと思ってやっている人が多くいるわけです。市場原理というものに対する、社会的コンセンサスがあるのかどうか。日本では資本主義が重要だと思っているのか時々わからなくなります。
日本企業のガバナンス改革
遅々としてしか進んでいない
芳賀 企業側のコーポレートガバナンスが、例えば企業側のミクロと、政策側のマクロと、両方一緒にならないといけないというときに、日本取締役協会もいろんな政策提言をされています。企業側の努力で政策側をさらに動かすためには何が足りないでしょうか。
宮内 企業側というのは執行部です。執行部からいうと、干渉されないのが一番いいのです。執行部が頑張らないといけないと思ってくれるにはどうしたらよいかというと、必要なのはマーケット・プレッシャーです。楽にやっていたら、いつのまにか株価が下がってしまう、一生懸命やっているところと大きな差がついて大変だという、プレッシャーがないといけないのに、日本では驚くほどマーケット・プレッシャーがない。マーケットをよくしていくイニシアティブを誰がとっているかというと、官庁や取引所です。規則で社外取締役を入れろといったら1人入れる、3人といったら3人、これで大丈夫という話ではない。
芳賀 そういう意味では、今の既存の日本企業のボードの中で、その会社の株価の状況について、どこまで深く議論しているのでしょうか。どうご覧になっていますか。
宮内 あまり議論にはならないのでしょう。今の日本のガバナンスで社外取締役を入れていますが、真の独立性はあまりない。CEOの気に入った人や知人、友人等が多い。誰が社外取締役を指名するか、指名委員会が執行部から独立して社外取締役を選定することがない限り、人数をいってもダメです。指名委員会の不作為、わかっていないとしかいえません。
芳賀 まだまだ日本企業では「うちは任意の指名委員会だから、これくらいでよい」と思っている会社が多いのではないかと思います。
宮内 お友達ばかりではガバナンスではありません。執行部のラバースタンプを押しているようなものです。数だけいるというだけの話です。日本の今のガバナンスはせいぜいその程度にすぎません。指名委員会で一番大事なことは、CEOを交代させることができるかどうかです。日本で多くの業績の不十分な会社があるのに誰も動かない。欧米では考えられないことが、日本の知られた会社で当たり前のように行われているのですから。ガバナンス改革が着々と進んでいるとどこかに書いてありましたが、私は遅々としか進んでいないという認識です。
芳賀 ガバナンス改革については、政府側も、数字だけみて順調と思っています。
宮内 政治側は十分わかっていません。企業側でもわかっていないのに、政治側がわかるはずがない。例えば、日本の会社法は企業経営の実体も十分わからない法制審議会などで主に法律の専門家が決めているわけで、その結果、3つも性格の異なる機関設計をつくり、これはいったい何を目的としているのか不明です。3つのうち、あるべき姿に近いと思う指名委員会等設置会社にも欠陥があることが明白ですが、それも変えない。このような制度設計の下では成長に資するガバナンスは生まれません。
芳賀 企業が機関設計の変更について議論する際に、運用をしっかりと議論すれば良いのですが、欠陥がある機関設計にとりあえず形を合わせようとすると、無意味な形式だけの機関設計の変更になってしまいますね。
宮内 本当に、外形的な数合わせが始まっているのだと思います。
芳賀 日本取締役協会では個人会員が最近増えていて、そういう方々と意見交換する機会を私もたくさん頂いています。お友達ではなく何らかの選択プロセスを経て社外取締役になられた方が、実際に就任後、自分の知識をどうアウトプットしていいか悩んでいるケースもあります。
宮内 そこでどうして悩むのかよくわからないのです。率直な意見を申し述べるために入っているのだから、それをしないとしたら何なのか。躊躇する理由は全くないです。
芳賀 躊躇しているというよりは、いわなければいけないことはわかっていても、いい方によって相手(取締役会)が本当に動くかどうかを悩んでいる。いっても伝わらない、伝え方が難しい、その辺りの問題かと思います。
宮内 基本的には、伝え方の問題ではなく、社外取締役が2人や3人ですと動かすのは無理でしょうね。よい参考意見を聞かせて頂いたと執行部は思うかもしれませんが、やらないといったらおしまいですから。そういう意味では、過半数の社外取締役が入っている取締役会でないと無理です。
会社形態の機関設計
不断の見直しが必要
芳賀 先ほどの機関設計の問題ですが、過半数が社外取締役になって、きちんと意見をいっていくような体制が先にあるべきでしょうか。
宮内 制度設計はものすごく重要ですが、日本は1回変えたらてこでも動かないというような形になっている。それに加えて、マーケット・プレッシャーがない。日本の投資家は何を考えているのか。投資目的がしっかりしていないので、アクティビストからみたらこんなに楽しいところはない。アクティビストはけしからんといっているけど、いっている方が十分実情を理解していないと思います。
芳賀 そうすると、日本の投資家のプレッシャーが足りないことと、受ける側のボードがプレッシャーに対してもっと向き合わないといけないことの両方が必要でしょうか。
宮内 両方だと思います。ですから、ダメな会社の株は売るという行動をとってもらわないといけないわけです。よいところはもっと買う。妙なアクティビストが入ってきたら急に上がるなど、日本のマーケットは感性がないというか、反応しないというか、不思議だと思います。
芳賀 少し海外の大きなところが入ってくると、途端に変わりますよね。
宮内 マーケットが弱すぎると思います。ガバナンスが整ってきた欧米では、政府が主導したというのはあまり聞いたことがなく、マーケットが主導してやむなく、嫌々でも執行部がついてきたわけです。
芳賀 それは日本の場合、企業側の開示の問題なのか、投資家側の問題なのでしょうか。
宮内 開示は相当されているのではないでしょうか。そっちの方が進んでいるように思います。投資家に問題があると思います。投資家というか、アナリストやファンドマネージャーなど、そういう人の眼力と実行力が弱すぎると思います。ウォールストリートやロンドンは狩猟民族ですから、ハンティングワールドの面白そうなものに食いつく、日本はアグリカルチャーですから、隣のおじさんが動き始めたら動くというような、この感性を何とかしないといけない。そういう人の感性とマーケットというものとがなかなか合わないですね。
芳賀 投資家側も、昔からいる投資家と、悪い意味ではなく提案型の物言う投資家のような新しい方々と、2つに分かれると思いますが、もっと後者が出てくればいいのでしょうか。
宮内 物言う株主を忌み嫌う風潮がありますが、彼らのいっていることの半分位は間違っていないと思う。いい加減なことをいっている部分もありますが。よいところを取っていったらいいのだと思います。
芳賀 そういう対話や意見を積極的に取り入れる前に、まず聞くという姿勢が足りないのですね。
宮内 聞いた方が得だと思いますね。いわれるだけの欠陥があるのですよ。物言う株主に入り込まれる会社というのは穴があると思い、変革のチャンスにすることではないでしょうか。
芳賀 入られるべくして入られた。そうすると企業側は、投資家からのプレッシャーがかかるような状況になってはいないのか、常に自社の状況を見ていかないといけないですね。
宮内 そう思います。おそらく、社外取締役がしっかりしていれば、そういうことが大きなテーマになるはずです。
芳賀 そこに社外取締役の重要な役割があるのですね。
社外取締役が果たす役割
会社の流れをモニタリング
宮内 日本は社外取締役になったらたくさん会議に出て、監査委員になったら工場のラインまでチェックにいく。そんなことをやる必要はなくて、もっと大きな目で会社の流れを見て、この社長に任せておいて大丈夫か、それを中心に考えればいいのです。
芳賀 会社の情報を把握していないと社外取締役の仕事ができないとおっしゃる方もいます。でももっと違うところをみていないといけませんよね。
宮内 そんな細かいことをみろなんて誰もいっていない。マクロのところを大きな流れでみないといけない。世の中の流れと違うことをやっているぞ、とのマクロビューだけでいいと僕は思っています。
芳賀 業界そしてさらに外のマクロの視点で、企業をモニタリングする。その為に社外取締役がいるわけですよね。
宮内 執行と同じになろうとするのはありえないです。改善するのに一番大事なのは、社外取締役の選び方、指名委員会がしっかりする。それから、社外取締役に指名された人が、私は何のためにきたのかわからない人が多くおられる。もう少し、日本でもプロフェッショナルな社外取締役を作っていくために、当協会がもっと教育しないといけないと思います。
芳賀 社外取締役の教育が、まだ知識的な部分の教育にとどまっているところがあると思います。
その業界にとらわれない大きな経済・社会の流れを踏まえ、企業がどのように大きな戦略を描くのか、つまり競争に勝ち続けられるのか、それを考えて取締役会にインプットし議論できるプロの社外取締役でなければいけないですね。そしてその点について社外取締役だけでの議論も必要ではないかと考えます。
宮内 お客さんみたいな気分で行っている人がいます。CEOと仲良くなってサポートしている。私は米国のボードに入っていたことがありますが、それはもうすごい緊張感です。そういう緊張感を作るのがボードだという認識がないですね。
芳賀 それはどういうふうにして教育し、わかってもらえるようにできるでしょうか。
宮内 悪いところを叩いてもしょうがないから、よい会社が昇っていくという、そういうロールモデルのようなものを作っていかないといけないと思います。
例えば社外取締役の選び方も、指名委員会が最後は決定するのですが、候補者を出すのは執行部ではなく。社外取締役で議論してヘッドハンター等のリストを絞って、インタビューして選んでいく。そこからどんどん変わっていって、本当の独立した取締役となっていきます。
芳賀 今日のお話を伺って指名委員会や社外取締役が本来やるべきことは本当に大きく、日本経済に最終的に影響することがよく理解できました。
宮内 本当に指名委員会が制すると思います。肩を叩くべき社長はたくさんいるのではないですか。
芳賀 同時に、退任していただく社外取締役もいるということですね。
宮内 もちろんそうです。本当に何しに入ったかわからない人がいます。もっと教育すべき、また勉強すべきだと思います。
芳賀 真面目で知識を多くインプットした人が悩むのはそこだと思います。女性で本当にやる気があって、社外取締役の勉強もしたいので研修も受けていらっしゃる方の方がそこで悩まれる場合が多い。会社によっては社長が気に入らないと社外取締役を1年でクビにしたりというのがあるようです。
宮内 ほかの社外取締役はそれを止めないといけないのです。
芳賀 おっしゃるとおり、社外取締役としての役割は一人の役割だけでなく、独立役員チームとしての機能が重要になりますね。当協会の研修の中でも、個々の社外取締役の質の向上だけでなく、チームとして機能するための研修も重要であると理解しました。ガバナンスの重要性が、今日のお話からとてもよくわかりました。
形式的にはものすごく正しくやっていて、社外取締役も時間を使い、業績もそこまで悪くないのだけれど、これでいいのかなというような会社もありますし、本当に難しいと思います。一部のサラリーマン社長の中には、もう少しプレッシャーをかける必要がありますか。
宮内 日本は90%ぐらいサラリーマン社長です。とんでもない人がなっているわけではなく、真面目でその人としては一生懸命やっているわけです。そういう意味では何が欠けているかというと、企業を成長させ経済を豊かにすることが最終的な使命だという自覚ではないでしょうか。市場のなかで勝ち抜く為の知力、決断力を持ちリスクに立ち向かって新しい富を生み出す責務があるのです。これを側面から監督し、力づけ、評価するのがガバナンスだと思っています。

宮内義彦
Yoshihiko Miyauchi
オリックス株式会社 シニア・チェアマン
1960年日綿貫業(現双日)入社、1964年オリエン卜・リース(現オリックス)入社、1980年代表取締役社長・グループCEO、2000年代表取締役会長・グループCEO、2003年取締役兼代表執行役会長・グループCEO、2014年より現職。2002年から2022年まで一般社団法人日本取締役協会 会長。2022年より同名誉会長。

芳賀裕子
Yuko Haga
名古屋商科大学ビジネススクール 教授
慶應ビジネススクールMBA 修了後、プライスウォーターハウスコンサルタントにて国内外大手企業の戦略コンサルティングに従事。その後、総合電機メーカー、産業機械メーカー、保険会社等大手企業のヘルスケア分野への新規参入コンサルティング、ベンチャー企業の取締役や執行役員なども歴任。協和キリン(2019~2025年)、エア・ウォーター(現)、ミネベアミツミ(現)の社外取締役も務める。専門は企業戦略とM&A。博士(経営学)。日本取締役協会 取締役研修委員会委員。
撮影:小泉賢一郎
これまでの記事[ SPECIAL TALK ]
- LEGENDS & THEIR HEIRS レジェンドとその想いを継ぐ者 馬越恵美子×松田千恵子
- Special Talk:識者に聞くコーポレートガバナンス 宮内義彦×芳賀裕子
- 女性活躍推進ワーキンググループ活動報告
- LEGENDS & THEIR HEIRS レジェンドとその想いを継ぐ者 吉丸由紀子×藤木貴子
- TALK & TALK:冨山会長が聞く~コーポレートガバナンスの最前線 東原敏昭×冨山和彦
- LEGENDS & THEIR HEIRS レジェンドとその想いを継ぐ者 宮井真千子×安田結子
- LEGENDS & THEIR HEIRS レジェンドとその想いを継ぐ者 橘・フクシマ・咲江×中島好美
- TALK & TALK:冨山会長が聞く~コーポレートガバナンスの最前線 太田洋×冨山和彦
- TALK & TALK:冨山会長が聞く~コーポレートガバナンスの最前線 磯崎功典×冨山和彦
- TALK & TALK:冨山会長が聞く~コーポレートガバナンスの最前線 翁百合×冨山和彦
- SPECIAL TALK:識者に聞くコーポレートガバナンス 久保利英明×高口綾子